【イベントレポート】JST-RISTEX CAREFILオープンセミナー 日本におけるケアリング・ソサエティへの課題―ケアの倫理の視点から
- YCARP

- 2025年7月4日
- 読了時間: 7分
2025年6月7日に「JST-RISTEX CAREFILオープンセミナー 日本におけるケアリング・ソサエティへの課題―ケアの倫理の視点から」を会場(ウィングス京都セミナーA/B)とオンラインでのハイブリッド形式で開催しました。44名(当事者8名、一般33名、不明3名)の方にご参加いただきました。
CAREFILプロジェクトの大きな目的として、ケアラー支援の理論化があります。
ケアラーへの支援を充実させるために、どのような理論化が必要なのか。CAREFILプロジェクトでは、ケアする人/される人という閉じた関係を前提にケアを代替することで負担軽減につなげる支援やケアする/しないの二者択一の考え方に留まることなく、人生のなかで誰もがケアに関わることを前提にケアをより広い視点で捉え、社会のなかで「ケアの価値」をいかに高めていけるのかという視点に立っています。
今回のオープンセミナーでは、そうした視点に立って「ケアラー支援」の道程を探るべく、同志社大学の岡野八代先生に、フェミニズムから生まれた政治思想である「ケアの倫理」についてお話いただきました。
【講師】
岡野八代先生
同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教員、専門は西洋政治思想史・フェミニズム理論。
現在の関心――歴史的に女性たちが担ってきた無償のケア労働の社会的、政治的意義を分析することを通じて、既存の政治学が理解する政治概念を見なおす研究をしている。
主著に『ケアの倫理と平和の構想――戦争に抗する 増補版』(岩波現代文庫、2025年)、『ケアの倫理――フェミニズムの政治思想』(岩波新書、2024年)、『ケアするのは誰か?――新しい民主主義のかたちへ』(白澤社、共著、2020年)、『フェミニズムの政治学――ケアの倫理をグローバル社会へ』(みすず書房、2012年)など。
訳書に、ジョアン・トロント『ケアリング・デモクラシーーー市場、平等、正義』(勁草書房、2024年)、エヴァ・フェダー・キテイ著『愛の労働 あるいは依存とケアの正義論 新装版』(白澤社、2023年)、アイリス・ヤング著『正義への責任』(岩波文庫、2022年)、ケア・コレクティブ著『ケア宣言――相互依存の政治へ』(大月書店、2021年)、など。
【当日の概要】
前提として、ケアの倫理におけるケア理解は、ケア関係を母子関係に留めず、むしろなぜ生物学的な女性を前提とする母子関係にケアが押し込められてきたのかを問い、より広い社会的文脈で考えます。こうしたケアの倫理の視点から、人間性や社会性を捉え直します。
今日におけるケアの評価の低さの背景には、歴史的に(健常)男性中心主義の政治学において長らく「自立」した人間が前提とされてきたことがあります。男性中心主義の社会には、「依存」への恐怖感があり、家事労働や肉体労働といった「依存」を伴うケアは否定されてきました。そのため、実際には依存している相手である女性や奴隷といった人々を非人間的存在とみなすことで、非人間的行為としての家事労働と肉体労働を女性や奴隷に割り当ててきたのです。
今でも民主主義の起源として賞揚されることの多い古代アテネの直接民主主義は、女性や奴隷に家事労働や肉体労働を押し付けることで成立していたという側面があるのです。
既存の正義論は、「自立」した人間を前提とし財の公平な分配など「平等」という普遍的な価値に基づいて人々の行動を判断するものである一方、ケアの実践から生まれてきたケアの倫理は、一人ひとりの違いを尊重するものであり、人々の行動をそれぞれの人がおかれた状況や条件、他者関係によるものとして、文脈依存的で社会的な問題として捉えます。こうした視点に立つケアの倫理は、一見ケアを自主的に選んでいるようにみえる人であっても、それは個人の自由な「選択」として放置できないのではないか、一部の人にケアを押し付けてきたのではないかという問いかけをします。ケアの倫理の視点から社会を捉え返すと、エヴァ・フェダー・キテイが「みな、誰かお母さんの子ども」というように、みな誰か生きていくうえで他者からのケアを必要とするという普遍性・価値がみえます。
こうした話から日本社会に視点を広げると、大沢真理のいうように内助をあてにした「自助」となっており、ケアは社会で支えられるものとはなっていないことがわかります。ケアを「家族」に閉じ込めず、ケア関係を社会へ開いていくことが必要であるものの、男女ともに有償・無償をあわせた総労働時間が長く、時間的に限界まで「労働」をしている実態があります。ジェニファー・ネデルスキーらがいうように、賃労働時間をより短縮させることを普遍的にするなどの大胆な提案も含めて、ケアを前提にした社会を変革的に創造していく必要があるのではないでしょうか。

【参加者感想文(一部抜粋)】
地方自治体公務員、社会福祉士です。国家や自治体、行政は外にあるものでなく、市民の意思決定の元にあるはずですが、そう意識されづらいことが課題だと思いました。また、職務上、障害者虐待やDV対応などを長く経験してきたなかで、ケアを家族に閉じ込めることの危うさは切に感じている一人です。男性だけでなく、女性もマッチョな仕事の仕方を求められる社会(私も超長時間労働で、外資系企業の夫がいなければ、職務上求められる業務がこなせない状況です)では、コミュニティにアクセスする余裕は持てず、社会が成熟するのが難しいのだと思います。京都の町衆の自治文化は本来の力を発揮できればより良いものになるのではと思いました。
最初は少し難しいかなと思いましたが、ケアということの政治学的、世界的、歴史的、日本的位置づけと流れについてはナルホドと知ることが出来ました。また、ケアする権利ということの持つ意味については非常に共感出来ました。私は精神障害の当事者ではあるけれど、地域での活動当事者でもあり、家庭内では多くの家事を担う女性でもあり、そういう様々な立場で感じる問題意識をごちゃ混ぜにして、整理して発信をしていけたらいいなぁと思えました。自分の人生は充実しているし、人にも恵まれていると思うけれど、その余裕があるからこその社会的活動のあり方を考えていきたいです。今回もありがとうございました!
「政治(国家)学」への苦手意識がありましたが、こんなに自分につながるのか、ケアの排除につながってきたのか、と。刺激的な学びの機会でした。ケアリング·ソサイエティに向けたプロセスの議論を積み重ねたいと思いました。ありがとうございました!
今まで私の中にはなかった考え方でした。講演を聞きながら、自分が言われた「女の子だから安心ね」という言葉に感じていた違和感や苛立ちの正体がハッキリしたような感覚でした。別の予定があり、途中で抜けてしまい申し訳ございませんでした。またイベントがあれば、参加させていただきます。今後もよろしくお願いいたします
貴重なご講演を拝聴させていただき、誠にありがとうございました。特に印象に残りましたのは、ケアを担う人々(主に女性)が、肉体労働者よりも劣る存在として位置づけられ、その結果として排除されてきた/現在も排除されつつあるというご指摘でした。岡野先生がおっしゃっていたように、現代社会における「自立」とは、他者への依存を否定し、他者を非人間的に扱うことによって成立・語られているのではないか、という点は非常に示唆に富んでいると感じました。この視点から考えると、家父長制社会における男性の「自立」というイメージ(いわゆるジェンダー・ステレオタイプ)は、女性を理想的な人間像から排除することを前提として構築されてきたのだと思われます。さらに、外国人や移民に関しても、彼らが「日本人」よりも劣った存在(たとえば低賃金で雇える労働力)として扱われている現状があり、日本の政治政策や社会制度が、そのような外国人・移民像を積極的に作り出すことで、排外主義的な意識の形成に一定の影響を与えているのではないかと感じました。今後もし機会がありましたら、岡野先生によるフェミニズムの視点からの移民政策や日本社会における多様性のあり方についても、ぜひお話を伺えますと幸いです。
【次回のお知らせ】
次回のオープンセミナーは、2025年9月21日(日)「CAREFILオープンセミナー/YCARP4周年記念イベント 外国ルーツのヤングケアラー支援・ケアラー支援―言語のケアを考える」を開催予定です。(詳細決まり次第ホームページでお知らせいたします)


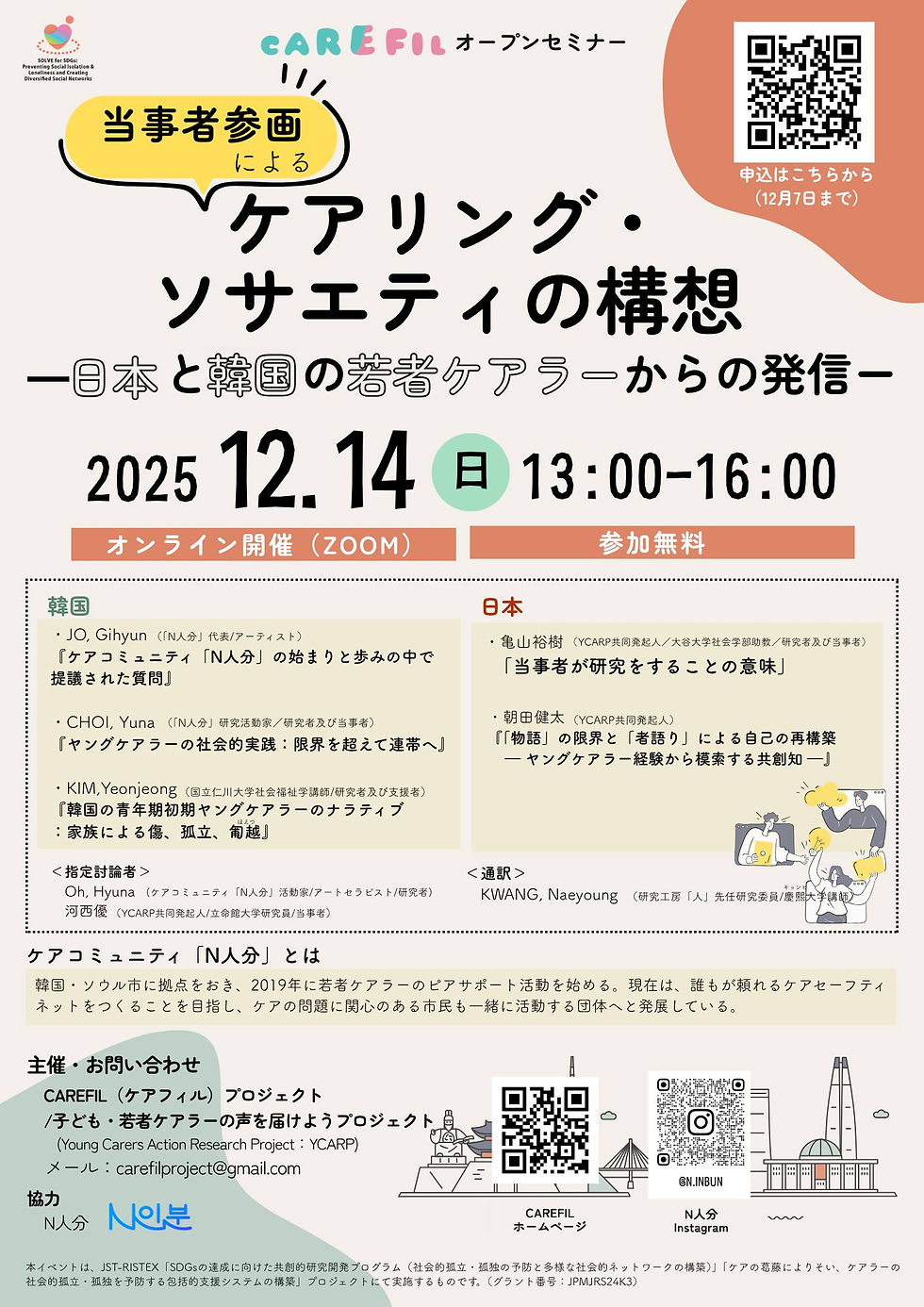

コメント