【イベントレポート】JST-RISTEX CAREFILキックオフイベント 第3回日本版ヤングケアラーアクションデー ケアラーのメンタルヘルス支援―EU Me-We Projectの取り組み
- YCARP

- 2025年3月18日
- 読了時間: 6分
2025年3月8日に「JST-RISTEX CAREFILキックオフイベント 第3回日本版ヤングケアラーアクションデー ケアラーのメンタルヘルス支援―EU Me-We Projectの取り組み」を開催しました。46名(学生・当事者7名、一般39名)の方にご参加いただきました。
今回で、3回目の開催となる日本版ヤングケアラーアクションデー。JST-RISTEXの委託を受けて開始したCAREFILプロジェクトのキックオフイベントでもありました。
今年は、日本ではまだあまり注目されていないように思われる「ケアラーのメンタルヘルス」をテーマに、ヨーロッパにおいて成人期への移行期にある15~17歳のヤングケアラーの回復力(レジリエンス)強化や、メンタルヘルスとウェルビーイングの促進に焦点を当て、彼らの生活における心理社会的要因と環境的要因の悪影響の軽減を目標としている研究チーム「EU Me-We Project」から4名(レナート・マグヌッソンさん、ミリアム・スヴェンソンさん、エミリア・オーべリさん、ヨハンナ・ミランダ・スコルドさん)にお話をいただきました。
※当日、エリザベス・ハンソン教授は体調不良のため、ご欠席されました。
【ME-WEプロジェクトの概要】
EUの「ホライズン2020」研究・イノベーションプログラムによる資金提供を受けた多国間プロジェクト。
期間:2018年1月-2021年6月
参加国:スウェーデン、オランダ、イタリア、イギリス、スロベニア、スイス。
目的:若者のレジリエンス(回復力)を高め、(家族、学校、仲間、サービス機関からの)社会的支援を強化することで、思春期のヤングケアラーのリスク要因を軽減すること。
今回の講演のなかでは、ME-WEモデルを中心にお話をいただきました。ME-WEモデルは、一次予防のための心理社会的介入を、思春期ケアラー当事者たちと専門家が共同で設計、開発、テストするものであり、グループセッションとモバイルアプリで構成されています。
ME-WEモデルは、アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)とポジティブ心理学をルーツとするDNA-Vモデル(Hayes & Ciarrochi, 2015)を基盤にしてグループセッションが行われます。
ME-WEモデルで行われるグループワークは、ケアラー自身のストレス思考にアプローチをかけたり、セルフ・コンパッション(自己への思いやり)を高めたりといった個人のストレスへの働きかけだけではなく、ケアラーたちがピアと出会う場にもなり、社会的なネットワークとしても重要な役割を果たしています。グループセッションで使用されるDNA-Vモデルは、思春期ケアラーがもつ固定観念を相対化し柔軟な自己観念を涵養しながら、ケアラー同士がお互いに支えあうことができるような社会的ネットワークづくりを視野にいれています。また、グループセッションに参加できない遠隔地のケアラーのために、モバイルアプリも開発されています。孤立しがちなケアラーのために、ネットワークづくりを重視している点はこのプロジェクトの特長といえます。
講演のなかでは実際にME-WEモデルのなかで実施されているマインドフルネスのレクチャーも行われ、自分のなかにあるネガティブな感情を肯定的な感情へと転換する方法などについて知ることができました。
ME-WEプロジェクトの調査結果によると、多くの参加者がグループワークへの参加に価値を感じ、自己評価も高まったと回答しており、学校の出席率や成績にもいい影響を与えるなど、思春期ヤングケアラーのウェルビーイングの増進や彼らのレジリエンス(回復力)の強化に貢献する可能性を秘めているそうです。
ME-WEモデルに関心のある方向けに、リンネ大学とthe Swedish Family Care Competence Centreによって、教育およびサポートパッケージが提供されています。
★サポートパッケージの内容
・ME-WEマニュアル
・ME-WE教育 –「トレーナーのトレーニング」
・ME-WEの体系的なフォローアップ/評価アプローチ
・相談およびスーパービジョン
・オンラインの国際ME-WEネットワーク会議
講演後の参加者からの質疑応答のなかでは、ME-WEプロジェクトにつながるきっかけとして、SNSよりも、子どものことをよく知る教師やソーシャルワーカーなど子どもたちと信頼できる関係を築いている大人たちからの紹介であることがわかり、あらためてオフラインでの日常的なかかわりの重要性が示唆されました。
孤独・孤立しがちなケアラーにとって、社会的なネットワークができるだけではなく、ネガティブな状況や感情に対してのアプローチ方法を知ることで、学業や生活に対して肯定的になる一つの方法として参考になったのではないでしょうか。
YCARPでも、こうした心理的なサポートもとりこみながら、ケアリングソサエティの実現に向けた社会資源の開発に取り組んでいきたいです。
【参考資料】
Hayes, L., Ciarrochi, J. (2015). The Thriving Adolescent: Using Acceptance and Commitment Therapy and Positive Psychology to Help Teens Manage Emotions, Achieve Goals, and Build Positive Connections. New Harbinger Publications: Oakland, CA, USA.
【参加者感想分(一部抜粋)】
私は精神科病院で心理師として働いておりますが、要因を紐解いていくと、幼少期よりヤングケアラーであることがとても多いです。当事者の方の困難な状況に度々胸が痛くなります。病院ではこのような患者さんにACTを用いて対応することも多いです。しかし、当事者の方の様々な理由から治療に来なくなってしまうケースも多く、数か月の継続が難しいことが課題としてあります。ME-WEアプリ使用などの導入があれば、対応にも広がりができ、当事者の方にも継続した関わりが持てると思いました。事例などを通してさらに具体的に学んでみたいと思いました。
ME-WEグループに参加してみたいと思った。日本でもこのような活動をしてほしいし、参加したい。
私は精神疾患を持つ両親の子どものの立場であり、現在ケアラー支援啓発活動のゲストスピーカーや研究協力をさせていただいております。仕事としては、相談支援専門員という障害を持つ方のケアマネジメントを行う業務についております。自分がケアラーであることを自認したのは近年です。この仕事を目指した根幹の理由についても、自分のケア経験に基づいているということに気づいたのも同様です。それほどにケアは日常に当たり前にあり、ケアをすることは自分の人生に染み込んでいたのだなということを感じています。その一方で、自分自身をケアすること、守るということは、おろそかにしていたなと振り返っています。「断るスキル」「流すスキル」などは、自分が自認する前は特に持ち合わせておらず、「自分が頑張らねば」となり、ひきうけてしまいがちなところがあります。これが生きづらさにも繋がっていたのだなと思うこともあります。Me-weプログラムは、生きる上で大切なスキルを獲得することができる大切な機会であると思いました。自分と相手との関係性のバランスを保つことができるということは、とても重要です。日本にもこのようなプログラムがあり、そして浸透していくことで、ケアラーの心が癒やされ、また、自分らしさを構築することによる強さを得ることができるのではないかと、希望を感じました。


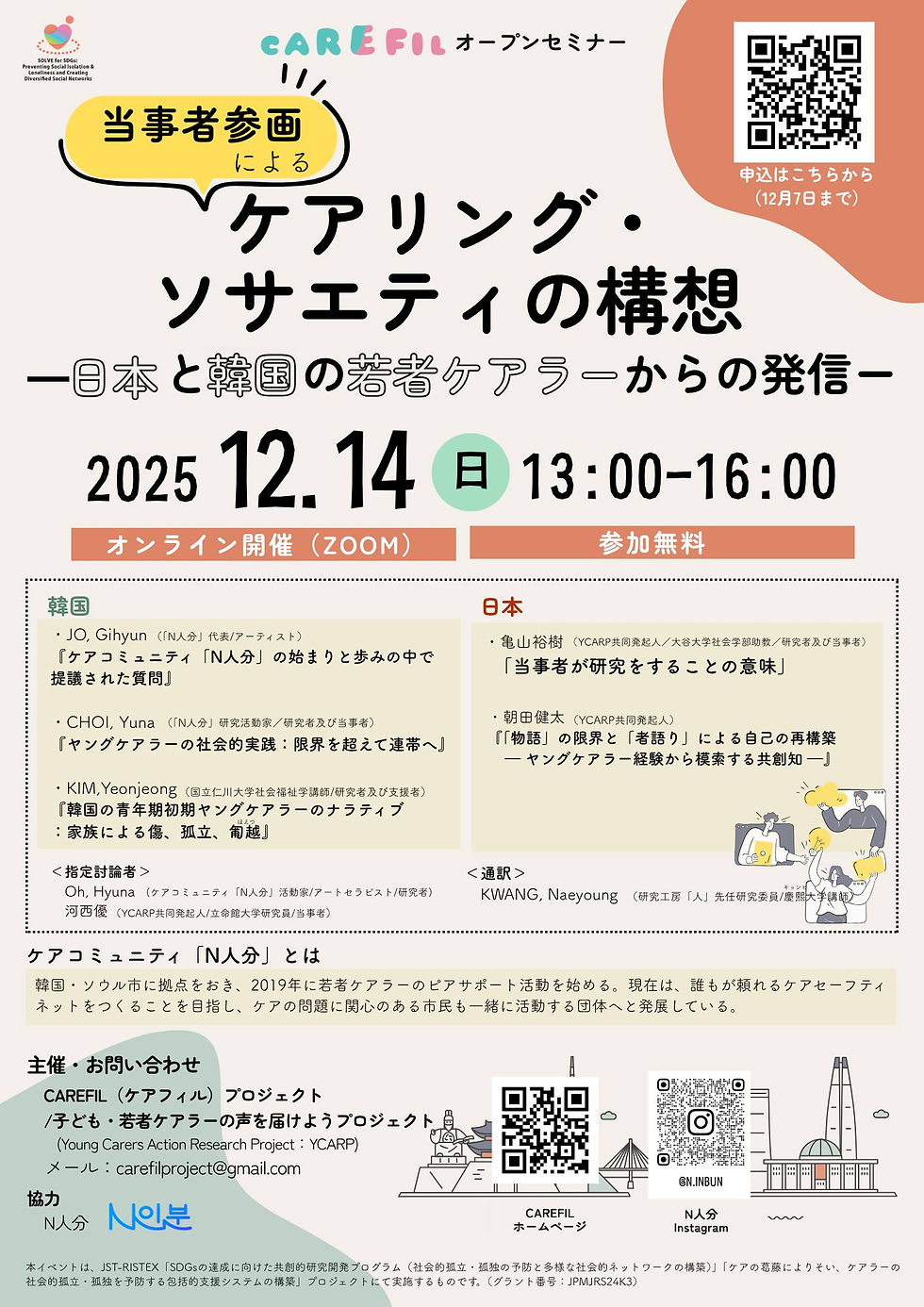

コメント